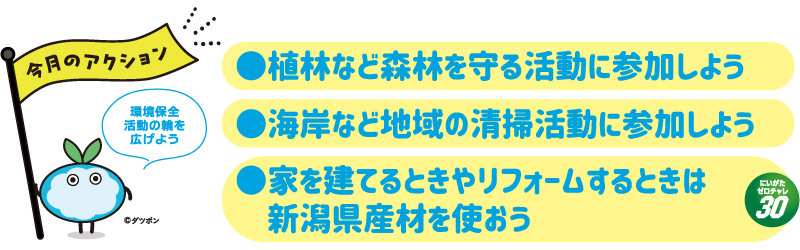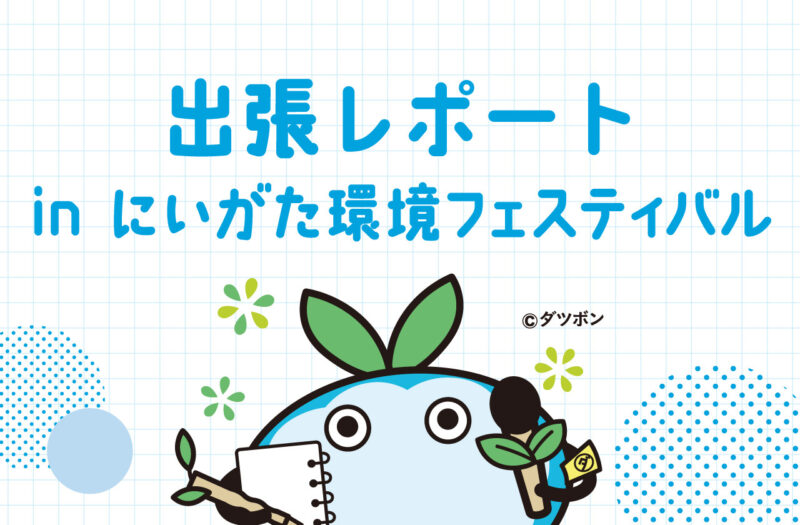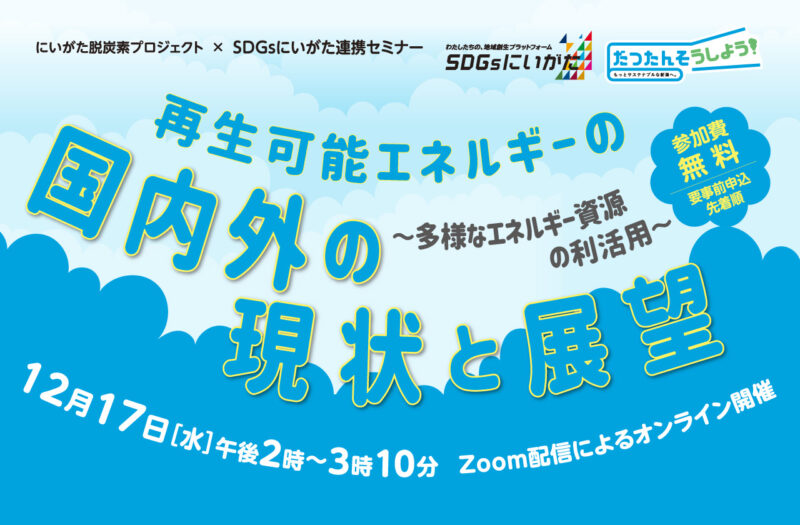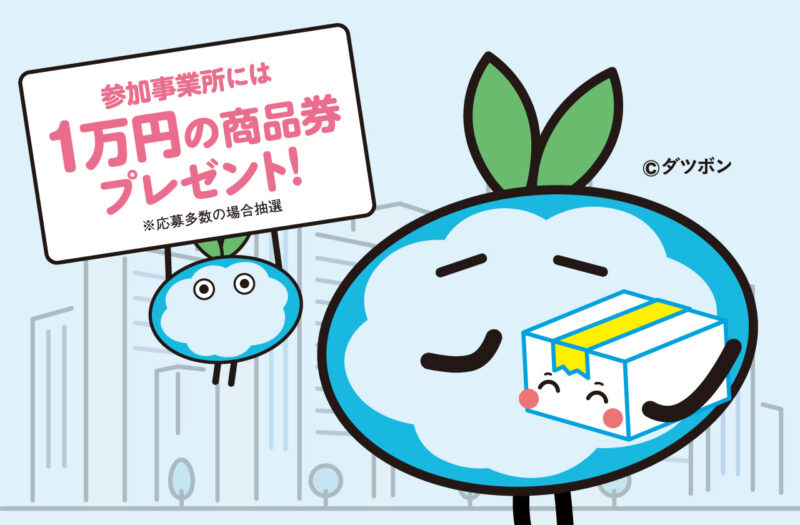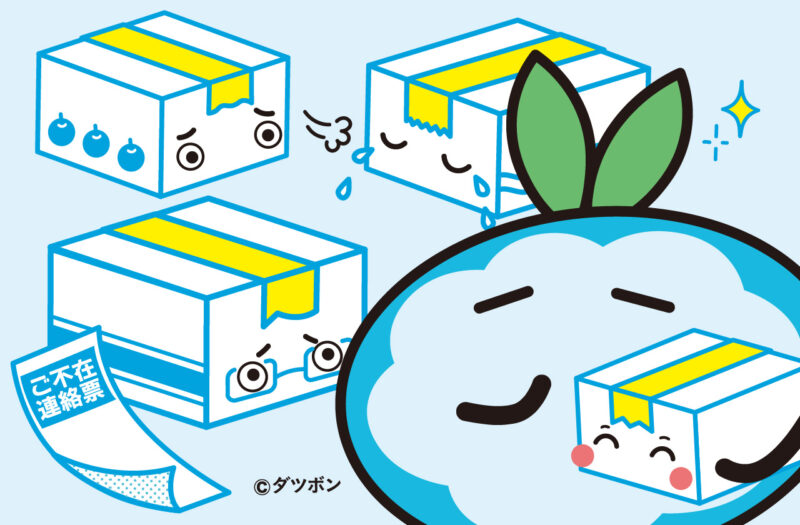- 紙面シリーズ
ふやせ、緑! へらせ、海のごみ!

地球温暖化防止へ、植物が重要な役割を果たしている。地球温暖化の原因とされる温室効果ガスのうち最も割合の多い二酸化炭素(CO2)を、森林などが光合成により吸収・貯蔵してくれる。ただ、森林の適切な管理が行われず、樹木の高齢化が進むと、吸収能力が低下していく。脱炭素社会の実現に向けて、まず県内から、自然を守る取り組みを進めてみよう。
CO2吸収 森林が貢献
国内の温室効果ガス排出・吸収量は、環境省によると2022年度(CO2換算)が10億8500万トン(排出量11億3500万トン、森林など陸上の吸収量5020万トン)で2013年度以降、ほぼ年々減少している。排出量は削減が続いているが、森林吸収量は低下傾向にある。森林の高齢化でCO2吸収量の多い、若い森林が徐々に少なくなっており、林野庁によると伐採後の再造林も進んでいないという。
こうした中、地域住民が、地元の森林を守ろうと植樹活動に取り組んでいる。先月下旬、阿賀野市の「五頭山麓うららの森」で地域の子どもら約50人が参加した植樹会が開かれた。参加者は、花びらが白色からピンク色に変化していく、サクラの珍しい品種「結桜(ゆいざくら)」の苗木約20本を、丁寧に植えた。
この植樹会を主催したのは、新発田地域緑化推進協議会。新発田、阿賀野、胎内の3市と聖籠町において、県民運動「にいがた『緑』の百年物語」の取り組みを担っている。「緑の遺産づくり」をテーマに運動に取り組む会長の鬼嶋正之さん(77)は「森林は、県内でも荒れている。植樹など人が関わっていかないと駄目になる」と強調する。このような植樹活動に参加できない人も、家を建てる時やリフォームする時に新潟県産材を使うことで、地元の森が手入れされ、未来の森をつくることにつながる。


海藻等の吸収量 CO235万トン削減
また、海の中でもワカメやアマモなどの海藻・海草が、光合成によりCO2を吸収・貯留してくれる。ただ近年、埋め立てに加え、地球温暖化などの環境変化が原因で、活性化した巻貝類の食害により海藻・海草の群落(藻場)が長期的に衰退・消失することが問題になっている。また、CO2を吸収・貯留する機能を持つ海藻養殖場の面積も年々減少している。
これを受けて県水産海洋研究所は、粟島沿岸で藻場回復の研究をする一方、佐渡市北東部の黒姫沖ではアカモクやワカメなどの海藻養殖の拡大技術開発に取り組んでいる。また、県内の漁業者や関係団体もこれまでに藻場の回復に努めてきた。環境省によると、2022年度の海藻・海草によるCO2吸収量は約35万トンだった。海藻・海草による吸収量を算定したのは世界で初めてだ。
これ以上、海の環境を悪化させないために、海岸や海につながる川のごみを拾う清掃活動も大切だ。新発田地域緑化推進協議会長の鬼嶋さんは「体験は、脱炭素に貢献しているという意識の醸成につながる。一人一人が意識を持つことで環境保全活動の輪が広がってほしい」と話している。